Vol.215 |陶芸家 芦澤和洋

装う器たち
ドットやひょうたんが並ぶ緻密な柄の飴釉(あめゆう)の陶器や、鮮やかな朱を大胆に配した平皿、ワンポイントが新鮮なマグカップなど、洗練されたセンスが光る器たち。これらの食器を作っているのが、富士市北松野に工房を構える陶芸家、芦澤和洋さんだ。高校時代に陶芸に魅入られて以来、ブレることなくこの道を邁進してきた。
そんな芦澤さんの生み出す器は、その高い芸術性に加え、実用性への強いこだわりがファンの心をつかんでいる。使う人の日々の生活に無理なくなじみ、どんな料理を盛っても様になる懐の広さが最大の魅力だ。取材を進めていくうち、作陶する中で起きるあらゆる“予想外”を味方につけてしまうご本人の包容力こそが、使い手の自由度を高め、器の持つ可能性を広げているのだと感じた。
陶芸家として、どんな活動をされているのか教えてください。
現在はおもに、一般家庭でふだん使いしやすい食器を中心に制作しています。スリップウェアと呼ばれる、土と水を混ぜたゆるいクリーム状の化粧土=「スリップ」で模様を描く、イギリス発祥の陶器です。
取引のある販売店からは、店頭在庫やほかの商品とのバランスを見て発注があるので、それに合わせて制作して納品したり、個人のお客さまからの注文に応えたりしています。また数年前からは個展や企画展と並行して、作品をより広く知ってもらうために全国各地のクラフトフェアへ積極的に参加するようになりました。お客さまと直に接することで聞ける要望や意見を参考にして、後日工房でいろいろな方法を試すことも多いので、毎回宿題をもらってくる感覚ですね。それに、何を展示・販売するか、ゼロから構想を練ることで、発想を自由に広げられる機会でもあります。模様や形も含め、陶芸家としての創造性を発揮せざるを得ない状況に自分を追い込めるので、ぐっと前進できるんです。
地元での活動としては1年半に一度、富士宮市野中のアートギャラリー『space Wazo』で個展を開催していて、この4月にも多くの方が足を運んでくださいました。

スリップウェアの器
陶芸との出会いは高校時代だそうですね。
実家の蕎麦屋を建て替えに来ていた大工さんがたまたま趣味で陶芸をやっていて、面白いよと誘われて行ってみたのが最初です。富士宮市柚野の陶芸家、今野登志夫先生のところで見よう見まねでいろいろ作るうちに、焼く工程で作品が変化するところに奥深さを感じて、もっとこの世界を探求したいと思ったんです。美大に進んで幅広く制作をしていく中で、白磁や、土の感じが残る、一般的なイメージの焼き物である粉引(こひき)の技術を身につけました。
スリップウェアを手がけるようになったのは2010年頃ですが、独立して数年間は青白磁や粉引の器に取り組んでいました。でも大量生産の器に比べて粉引などは、油分の多い料理を盛ると小さなヒビから油がしみ込んでシミになってしまうのが難点です。一般の人にとっては“作家ものの器”というだけで敷居が高いのに、気に入ったものを思い切って買っても、すぐにシミができてしまったらショックですよね。そこでもっと日常の中で気軽に使える食器が作れないかと試行錯誤しました。伝統的なスリップウェアはもともと耐熱耐火の器で、日本でいう鍋のような厚くて重い、しみ込みやすいものです。その耐熱耐火の機能をなくす代わりに、軽くて強度のある器に作りかえた結果、今のスタイルに行きついたんです。
僕の場合、板状にした土の表面にベースとなる化粧土をかけ、さらに調合を変えた別の化粧土をスポイトで垂らして模様を描く方法で作ります。乾かしてから成形して焼くのですが、ろくろで作る深さのある器よりも、プレート類に向いている技法なので、和洋中どんな料理にも合うと思います。またドットなどを配したモダンな柄もスリップウェアと相性が良く、世代を問わず好まれていますね。それに、形が同じでも柄を変えることで多種多様な器が作れるところが魅力的に映りました。それまでに身につけた技法を応用できましたし、自分に合っていると感じて、結果的に今一番長く続けている製法です。

糸で切り分けて土を均等な厚さに

下地となる化粧土をかける

スポイトで垂らして模様を描く
作り手として、こんな風に使ってほしいという希望はありますか?
用途はいくつか想定してはいますが、基本的には自由に使ってもらいたいです。中には、少し高さのある器を見て「うちの猫のごはん皿に良さそう」と言われた方もいましたが、そんな使い方も大歓迎です。使いやすさを追求するため、お皿の大きさも従来の3寸、5寸という3センチ刻みではなく、その中間にしたり、ひょうたん型など独特のプレートでも縁には少し立ち上がりを持たせたりと、既存の枠にとらわれないようにしています。統一感は持たせつつ、まったく同じではない柄も、集める楽しみがあると好評です。
「自分が作ったから」よりも「使いやすいから」という理由で選んでもらえるのが一番嬉しいです。人の手に渡れば器が主役なのでもう僕は関係ありませんが、お客さまがSNSで投稿していると器のその後が見えて面白いですね。ある時は、猫が大きめの器にぴったり収まっていて、そんな使い方もあったかと笑いました。嬉しくて投稿にコメントすることもありましたが、作家がしばしば顔を出すと窮屈かなと反省して、今では我慢してそっと見るだけにしています(笑)。僕の器を使うことで「いつもの食卓が華やぐ」「器をこんな風に使うと楽しいんだな」と、それまでになかった心の回路がつながったり、ちょっとした感動が生まれたりするといいなと思っています。

偶然性を追い求めて
最新のコレクションは、とても色鮮やかですね。
白地にベンガラという赤で模様を描いたもので、昨年末の個展を機に新たに挑戦したものです。釉薬(ゆうやく)で色をつけるのではなく、化粧土自体の配合で、焼き上げた時に狙い通りの赤に発色させるのが難しく、納得がいくまで1年ほどかかりました。器の色は、大まかには化粧土と釉薬で決まり、化学式もあるのである程度は予想がつくのですが、イメージ通りにするためには結局のところ実際にやってみるしかないんです。化粧土の配合、釉薬、焼き時間、温度、窯の中の熱の上げ方など、無数の組み合わせから当たりをつけ、徐々に条件を狭めていってその色にたどり着きます。
陶芸は、知識と経験値を総動員してもやってみるまで答えがわからない、まさに“科学実験”。そのぶん面白いですし、失敗が新しいアイデアに転じることも珍しくありません。お風呂に浸かりながら翌日の作業を思い浮かべた時に、「前回の失敗とあの時の方法を組み合わせたらどうなるんだろう」とひらめいて、翌日工房で試すと良いものが出てきたり。また実際に手を動かす中で、意図しない偶然から発見があったりもします。
例えば、ドットはすぐ隣同士に描いても表面張力でくっつかないんだということも、やってみて初めてわかったんです。乾かす前に振動を加えて化粧土の厚みを安定させるのですが、その時の揺れで模様が予想外にいい変化をすることもあります。こちらの意思で絶対こうしようと進めるよりも、偶然性が新しい視点を与えてくれるんです。陶芸家としての姿勢も、必ず到達したいゴールを設定してそれに向かっていくタイプではありません。創意工夫しながら自分なりの作品づくりを積み重ねた先に、「これだ!」というものが見えるのだと信じています。

釉薬の違いで多彩な味わいが生まれる
工房には食器のほかにも、さまざまな植物用の鉢が並んでいますね。
知人の影響で多肉植物にハマり、マダガスカル原産のパキポディウムという植物を自分で交配して種から育てています。その流れで、せっかくならと10年前から植木鉢の制作も始めました。
仕事をする中で、撥水性が低くて器には向かないけど、温かみのある質感の釉薬ができることもあったので、そういったものを鉢に応用しています。土によって焼成に適した温度があり、それに達していないと器としては耐久性が足りないこともあるのですが、そのぶん柔らかさや表情が出るので、面白いものは鉢にしています。量産するわけではないので、希少な土を使うこともあります。基本的に鉢は一点ものなので、もし「何年か前に見たあの鉢がほしい」と言われても、同じものを作るのは難しいですね。
それに、器を作る上では使う人の評価が気になりますが、鉢についてはワガママ(笑)。器づくりが使う人ありきの仕事だとすると、鉢づくりはより作品的な要素が強く、そこで自己表現の欲求を満たしている感じです。それだけに、鉢を気に入ってもらえるのは器を褒められるよりも感性そのものを認められた気がして、喜びが大きいです。

マダガスカル原産のパキポディウム

芦澤さんが手がけた植物用の鉢
これからも、生まれ育ったこの土地で作品を生み出し続けていくのですね。
実家の蕎麦屋は兄が継ぎ、僕はどこで暮らしても良かったのですが、それでもこの土地に帰ってきたのは、心から大切だと思えるふるさとだからです。大学進学から10年近く地元を離れていた時期があったからこそ、余計にこの土地の良さを実感しています。幼い頃、友人と自転車を乗り回していた川と田んぼ、富士山が見えるお気に入りの場所に行くと、今でも美しさにハッとします。
原風景が作品に直接的に表れることはありませんが、根底のところで自分自身の血肉となり、自分の作るものにも自然と組み込まれている気がします。大好きな土地に工房を構え、安心感に包まれているからこそ、自分らしい作陶を続けられるのだと思いますね。今は県外での活動も増えましたが、ゆるぎない拠点があるからこそ世界を広げていけます。今後も器を通していろいろな人の日々の生活に寄り添っていきたいです。

Title & Creative Direction/Daisuke Hoshino
Text/Chie Kobayashi
Cover Photo/Kohei Handa
【撮影協力】 space Wazo

芦澤 和洋
陶芸家
1979(昭和54)年11月27日生まれ (45歳)
富士市出身・在住
(取材当時)
あしざわ・かずひろ / 富士宮東高校在学中に陶芸に出会い、京都精華大学美術学部造形学科(陶芸専攻)に進学。卒業後は山梨県忍野村の會田雄亮研究所に勤務し、壁面・練込の制作を行なう。研究所では数名の制作指揮を執るチーフを務めた後、2006年に地元である富士市北松野に工房『陶芦澤』を開設して独立。青白磁や粉引の器づくりを経て、2014年からはスリップウェアを制作する。偶然性を楽しみながら実験を重ね、新しい作風に挑戦し続けている。県内外での個展やクラフトフェア出展を通じて、全国各地にファンが多い。また、植物好きが高じて鉢の制作を始めて10年。感性のままに作る豊かな表情や味のある一点ものの鉢は、企画展などで定期的に発表している。
作品の取扱店舗
- Calm器&雑貨
富士市柚木232-13 - ハナレALTANA
富士市永田67-17 - 富士高砂酒造(酒器)
富士宮市宝町9-25 - Crafts & Atrs Shop 《iri》
三島市一番町2-34-101 - 基地 TESHIGOTO
熱海市咲見町12-10
陶芦澤 Instagram
Nutshell 〜取材を終えて 編集長の感想〜
太古の昔。人々が集落を作って定住し、農業を始め、一方で農産物の貯蔵や食事のための器を焼く技術が生まれ、やがて(縄文様で土器を装った縄文人のように)生活を彩る芸術性を帯びていき、以来ずっと器は我々の生活とともにありました。陶芸は人類史上最古の工業技術のひとつといえます。
結果がすぐ目に見えるであろう石器づくりと違い、土器づくりには「焼いてみなければわからない」ことがたくさんあったことでしょう。どんな土を使うのか、どのくらいの時間焼くのか、もう少し時代が下れば、どのような表面処理(釉薬塗布)をすると美しく焼き上がるのかなど、焼きものの世界はそれこそ古代から現代に至る職人たちの膨大な試行錯誤の上に成り立っています。だからこそ奥が深く、樹脂成型による大量生産が発展した現代においてもなお人を魅了し続けるのでしょう。
芦澤さんの工房でお話を聞きながら、技術の進化における2つの時間軸のことを考えていました。ひとつは、長い時間をかけて師匠から弟子へ、先人から後継者へと守り受け継がれてきた、ゆっくりと積み重ねられる進化。もうひとつは、職人(あるいは作家)個人のなかで模索しながら、受け継いだ技術から離れ、ときには破壊することで生まれる進化。これまで挑戦してきたさまざまな試行錯誤について語る芦澤さんの目は、まるで科学実験に夢中な子どものようでした。
生涯を創作に費やした芸術家の多くが年代ごとの作風を持つように、これから20年先、30年先、芦澤さんの作る器もまたさらに進化していく予感がします。この時代の芦澤作品、今のうちにぜひ手にしてはいかがでしょう。
- Face to Face Talk
- アート
- コメント: 0
関連記事一覧

Vol. 119|冨士日本刀鍛錬所・刀匠 内田 義基

Vol. 152|ワンダーラビット・クラブ 代表 匂坂 桂子

Vol. 217|おもちゃのキムラ 店主 木村 光亮

Vol. 201|核兵器廃絶平和富士市民の会 土屋芳久

Vol. 130|プロサッカー選手 川口 能活

Vol. 143|富士市なわとび協会 会長 西沢 尚之

Vol. 165|わんわん大サーカス 団長 内田 博章

Vol. 155|FUJICANDLE 蝋飾人 鍋山 純男
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
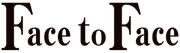
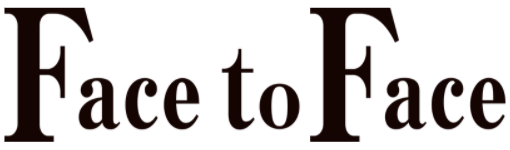
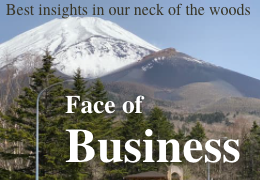
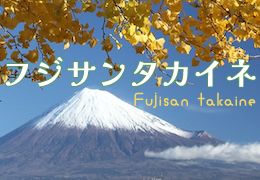

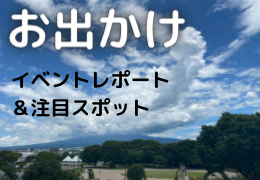





この記事へのコメントはありません。