Vol. 190|エンディングプランナー 中村雄一郎

家族が主役の葬儀
高齢化が進むと、さまざまな問題が出てきますね。
日本の福祉制度は生きている人を前提にしているので、被後見人が亡くなった時点で後見人との契約も切れてしまうんです。だからといって、四角四面に故人を放置することは心情的にもできませんよね。結局、死後のさまざまな手続きは、施設の職員や後見人の厚意に頼っているのが現状です。勉強するにつれ、世の中の実情に追い付いていない制度の問題点なども見えてきたので、弊社では、独りきりで施設で亡くなる高齢者の諸々の手続きと納骨までを一括して担当するプランの提供も始めています。
それに加え、離婚や死別、子どもと遠く離れて暮らす高齢の単身世帯が増えたことによる空き家の急増も、今や大きな社会問題です。単身者が亡くなり、その住まいが空き家になる瞬間に立ち会っているのはまさに我々葬儀会社なので、単身世帯の方の死後の不安を少しでも減らせるように、問題意識を共有してくれる不動産業者を募って昨年の秋から空き家の買い取りも始めました。
社会課題にも積極的に立ち向かっている印象です。
東日本大震災とコロナ禍によって、私自身、社会問題に対する向き合い方が変わりました。震災当時は都内の葬儀会社に勤めていましたが、発生から3ヵ月後に葬祭業者として協力するために宮城県気仙沼市に入ったんです。
まだあちこちに残るがれきの中から自衛隊が遺体を見つけ、警察が収容して遺体安置所として使われていた体育館に運びます。ここで、身元が判明した遺体をご家族とともに火葬場まで運ぶのが我々葬儀業者の役割でした。1週間の滞在中、7~8体のご遺体を運びましたが、県内の火葬場も被災しているため、秋田県まで行くのです。
3時間ほどの移動中、どの遺族も決まって口にするのが、「見つかって良かった」という言葉です。連日安置所に足を運び、100以上並んだ棺の中から、ほんの少しの手がかりをたどってやっと家族を見つけた時に湧いてくる思いは、そのひと言に凝縮されているんです。遺体を前にして弔ってあげられることが、遺された家族にとって唯一の救いだったんだと思います。そう考えると、コロナの第1波の頃、面会もできず、死に目にも会えない、遺体も引き取れず、ようやく対面できるのはお骨になってからというのは、家族仲が良ければ良いほど、想像を絶する苦しみであったはずです。
震災の経験があったからこそ、富士市内でコロナによる死亡者が出た場合の対応を行政から依頼された時には、迷うことなくお受けしました。まだ防護服などの装備もなく、手順も確立していない時期でしたが、誰かがやらなければいけないことですし、顔も見られないまま永遠に別れることになった遺族の気持ちを思うと、我々にできることはやるべきだという一心でした。間もなく実際に亡くなった方が出たと連絡を受け、遺族のいない病室で故人を棺に納めて火葬場へ運び、我々が収骨まで終えて骨壺を遺族に届けました。
震災やコロナ禍で、人の死は突然やってくると実感し、遺族の戸惑いや悲しみを目の当たりにしてきました。日常の尊さに気づいたのは私だけではないと思います。でも、時間が経つとつい忘れてしまうこともあります。それでも、何気ない日々の中で意識して家族との思い出を紡いでほしいと思います。
これから実現したいことを教えてください。
故人や遺族の思いに寄り添い続けると同時に、民間企業の強みを活かして社会課題にもどんどん取り組みたいです。
具体的には外国の方、特に富士市内に多く住むブラジルの方の葬儀に対応するため、ポルトガル語のホームページを準備中です。今までに2度経験がありますが、文化の違う異国で混乱する遺族を前に、このような方々にも情報を届けなくてはと強く思ったんです。
情報発信の面では、あまり知られていない制度について講座などを通じて啓蒙していくのも我々の重要な役割。たとえば、遺言に明記しておくことで、亡くなったあとに財産を法定相続人以外に寄付できる「遺贈寄付」という制度があります。故人の思いを社会に還元できますし、日本の金融資産の6割を高齢者が保有している現状において、資産を国全体に循環させる意味でも有益です。
ほかにも、墓じまいや永代供養が増えている今の時代、富士市の街なかに共同墓地があるといいと思います。高齢になって車を手放しても、街なかにお墓があれば、散歩がてら立ち寄って手を合わせられますよね。
今後も分野を限定せず、その時代や価値観に合う柔軟な提案をしていきたいです。地元に根を下ろす企業として、地域の人が、家族をはじめ周りの人たちと絆を深めて豊かな人生を送るために、我々に何ができるかを追求し続けます。

Title & Creative Direction/Daisuke Hoshino
Text/Chie Kobayashi
Cover Photo/Kohei Handa

中村雄一郎
かぐやの里メモリーホールエンディングプランナー/終活カウンセラー
1980(昭和55)年12月15日生まれ(41歳) 富士市出身・在住 (取材当時)
なかむら・ゆういちろう/静岡聖光学院中高、帝京大学法学部卒業。在学中に国会議員の秘書となり、卒業後も公設秘書として国政を間近に見る。議員関係の葬儀に数多く出席する中で業界に興味を持ち、葬儀会社に転職。2017年に地元の富士市で『かぐやの里メモリーホール』を設立。これまでの形にとらわれず、遺族が心から納得できる葬儀を作り上げている。エンディングプランナーとして現場に立ちながら、新聞での連載や、まちづくりセンターなどで一般の方に向けた終活に関する講演も行なう。東日本大震災やコロナの最前線で職務に当たった経験から、社会課題に対しても日々知識を深め、積極的で幅広い取り組みを実践している。

Nutshell 〜取材を終えて 編集長の感想〜
私は葬式というものが好きではありませんでした、と書くとそんなの当たり前だと言うかもしれませんが、「亡くなった方の“その人らしさ”を一番大事にした葬儀は意外と少ないんじゃないか?」と言えば、もしかしたら賛同してくれる人もいるかもしれません。私も地元の富士に戻ってから10年あまりの間に数十の葬儀に参列しましたが、故人とは面識のない葬儀がほとんどで、なんだか他人の家庭のプライベート空間に部外者として侵入してしまったような申し訳なさを感じることも少なくありません。でも実際のところ、多くの葬儀はそんな赤の他人を念頭に当たり障りなく企画されている面が否めません。
愛する人との死別というのは、人生の中で最も大きな、そしていつか必ず訪れる節目です。そして言うまでもなく、その主役は故人とその家族です。もっと当事者本位の葬儀があってもいいんじゃないか、というのが私の冒頭の感想につながります。
中村さんは「既存の葬式に違和感がある人の受け皿になりたい」と言います。それはつまり、家族の絆を最優先した、癒やしのための葬儀です。人が生き、思い出と絆を残して去っていく。葬儀とは本来もっと親密な場であっていいのではないでしょうか。
準備の時間が足りないままその日を迎えてしまうことも、葬儀がその人らしくならない要因です。「終わりが見えるからこそ豊かに生きるんです」という中村さんの言葉が印象に残りました。自分の人生を言語化してみるための「エンディングノート」を、元気なうちからつけ始めることを是非おすすめしたいと思います。
- Face to Face Talk
- コメント: 0
関連記事一覧

Vol. 110|チャイルド・ライフ・スペシャリスト 桑原 ...

Vol.209 |ダウン症モデル 菜桜

Vol. 115|富士山かぐや姫ミュージアム 館長 木ノ内 ...

Vol. 107|作曲家 渡井 ヒロ

Vol. 217|おもちゃのキムラ 店主 木村 光亮

Vol. 179|美術家/演奏家 白砂 勝敏

Vol. 210|武術太極拳選手 野田恵

Vol. 160|折り紙アーティスト 寺尾 洋子
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
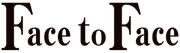










この記事へのコメントはありません。