「自然豊かな環境でのびのび学ぶ」 新しい選択肢 〜 富士宮市立人穴小学校 〜

コミュニティニュース
全国ニュースでもたびたび目にする、公立小中学校の統廃合。母校がなくなったり、地域で元気な子どもたちの声が聞かれなくなったりすることを想像すると、誰もが切ない思いを抱くだろう。
静岡県東部も例外ではなく、富士市では昨年、吉原東中学校が統廃合され、ほかの過疎化が進む地域でも各自治体の試行錯誤が見られる。沼津市では、戸田や長井崎、静浦地区で公立小中学校の一貫校化が進み、義務教育の9年間をひとまとまりとして捉えて教員の相互乗り入れを可能とするなど、新たな教育の形が生まれている。
そんな中、富士宮市の人穴小学校が「小規模特認校制度」を導入すると聞き、取材で訪問した。
小規模特認校制度を簡単にいうと、市内在住であれば学区外からでも通学が可能になる制度のこと。特定の小規模校で、特色ある教育を行なう場合に、自治体の教育委員会の審査を経て適用される。
富士宮市立人穴小学校は、JR富士宮駅から北に17キロ、車で約30分の場所に位置し、朝霧高原にも近く自然豊かな地域だが、市内でも特に過疎化が深刻で、今年度の全校児童は15名。年々減っていく児童数に危機感を覚えた保護者たちが、互いに学び合える児童数を保ち、できるだけ多様な人間関係を持続させたいと考え、この制度の導入を提案したのが始まりだ。

各児童への目配りは少人数の授業ならでは
人穴小小規模特認校制度推進係を務める安中真実さんは、人穴小の魅力をこう話す。「児童数が少ないからこそ、地域全体で子どもを育てる意識をみなさんが持っています。学校行事にも地域の方々が参加してくれますし、運動会も小学校と地区の合同です。私も人穴の自然環境と人のあたたかさに魅了されて、子どもが小学2年生の時に埼玉県から移住してきたのですが、多くの人たちから見守られてのびのび育つ子どもの姿に、通わせて良かったと感じています」。

体育や行事は全校児童みんなで賑やかに
日々の授業は2学年ずつが同じ教室で学ぶ複式のため、教室の前後の黒板を使い分けて行なわれるが、児童15名に対して教職員が11名という手厚さにより、きめ細かな指導が可能だという。体育など教科によっては全学年一緒に行なうため、異年齢の子ども同士の関係も深まり、きょうだいの数が少なくなっている今、かなり貴重だと感じた。ほかにも、一人ひとりが「主役」になる機会が必然的に増えることで、授業での発表やそれぞれに与えられた役割を通じて、表現力や自主性が育つというのもうなずける。
推進係の保護者が積極的に情報発信するインスタグラムなどのSNSからは、学校生活を全力で楽しむ子どもたちの充実感が見て取れる。通学を検討中の子どもや保護者が実際に体験・交流できる機会として、オープンスクールも開催されている。
7月のオープンスクールに参加していた5組の親子のうち、数名に話を聞いてみた。小学校入学を来年に控えた子を連れてきた母親は、「住んでいるのは大規模校の学区ですが、少人数で学校生活を送るほうがわが子に合うかもしれないと思い、見学に来てみました。児童一人ひとりに先生方の目が届くところがいいですね」と話す。ほかにも「一人っ子のため、他学年の児童ときょうだいのように密に学べるところが大きな魅力」と話す人もいた。ただ、懸念となるのは送迎の問題だ。放課後は隣の地域にある上井出小学校の学童保育を利用できるため問題はないが、登校時に自家用車で学校へ送り届けてから、自身の職場などに向かう時間のやりくりに不安を覚える保護者が複数いた。統廃合の場合は自治体が通学バスを運行することも多いが、小規模特認校制度では他校との平等性などの面から難しく、課題は残るだろう。

写真左から、推進係の安中さん、人穴小校長の遠藤さん、推進係代表の村澤さん、人穴区長の月岡さん。学校・保護者・地域が協力して子どもたちを育む。
この先、少子化の波が止まることは考えにくく、学校の統廃合が相次ぐ将来もそう遠くないかもしれない。そんな中でも大切にしたいのは、子どもたちにとって最善の環境だ。「私たち人穴小の保護者は必ずしも統廃合に断固反対しているわけじゃないんです。時代の流れは受け入れつつ、新たな制度の力を借りて、子どもたちの環境を良くするために今できることをやろうとしています」(安中さん)。
自然豊かな場所で児童同士や教職員のみならず、地域の人々も一緒になって深く関わっていけるのは小規模校ならではの大きな魅力だ。保護者の仕事や家族構成など各家庭での事情は異なるが、入学先や転校先の選択肢の一つとして検討する価値はおおいにあると感じた。
(ライター/小林千絵)
PTAのインスタグラムでは学校の様子を詳しく発信している。小規模特認校に興味があり、学校見学やイベントへの参加を希望する場合は、人穴小学校ウェブサイト内の各種フォームから問い合わせや申し込みが可能。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
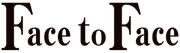
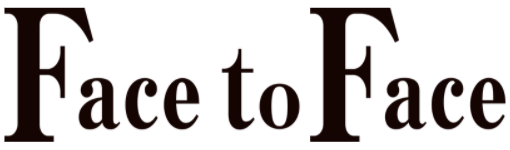
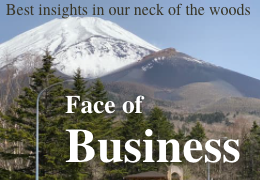
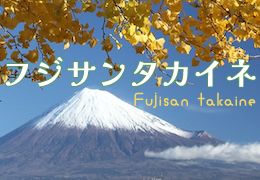

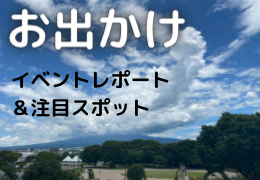













この記事へのコメントはありません。