Vol. 203|舞台衣装制作 小川 浩子

自然に着飾って
西洋占星術の分野で2020年末頃から始まったとされる「風の時代」。産業革命以降の価値観が大きく変わり、組織よりも個人の自由や権利が尊重される時代を指す。コロナ禍を経てそれまでの常識が一変した現代において、風の時代の空気感を快適に感じる人は少なくないだろう。
富士市・吉原商店街に衣装制作の場『アトリエテチ』を構え、一切の妥協なく依頼者の希望を叶える姿勢と、正確な技術で信頼を得る小川浩子さんもその一人だ。舞台芸術に携わる際には、周りと無理やり足並みをそろえるのではなく、それぞれが自身の役割を粛々とこなすことで、完成度はより高くなると話す。個を磨き、自然体で周囲の人々とつながることを大切にする小川さんの生き方こそが、風の時代を象徴していると感じた。
現在の仕事内容を教えてください。
地元の音楽家やダンサー、劇団員の舞台衣装をはじめ、都内で活動するアイドル、派手な化粧や髪形・衣装でロックを演奏するビジュアル系バンドの衣装を作っています。デザインに関しては、衣装を着る本人が集めてきた画像を参考に、「袖はこんな形で」「色は赤」などの具体的な要望を100%活かして作るので、私自身の個性を前面に出すことはありません。そこが「デザイナー」ではなく「衣装制作」と名乗るゆえんです。
依頼者の頭の中にはすでに自分の出演する舞台の世界観に合致した衣装があるので、そのイメージ通りのものを納品するのが私の役割だと捉えています。その中で、例えば激しい動きをするなら、腕の動きを妨げない素材を使ったり、体のラインをきれいに見せるために両サイドを締めるパワーネットという生地を使ってくびれを強調したり、制作者として技術とアイデアを総動員しています。それまで作ったことのないジャンルは毎回が勉強ですし、時代に合った感性を磨くため、日々SNSなどでの情報収集は欠かせません。
理想としているのは、身にまとうことで心の底から楽しめて「自分は輝いている」と感じてもらえる衣装です。本人が動きづらさや不自然さを感じることなく衣装と一つになれて、その人らしさを邪魔しないことが大切なんです。制作過程で細部に私の好みが入ることはありますが、あくまで着る人の世界観に合わせた仕上がりを意識しています。
他には年に数回、作品展に参加して衣装を発表する機会があります。ふだんと違って純粋に自分の好みを盛り込める楽しさもありますが、マネキンの一種でトルソーという人格のないものに着せるので、いつもとは勝手が違います。どう見せたいか、衣装とその周りの飾りつけなど、世界観を一から模索していくのも作品展の醍醐味です。




衣装制作の道に進んだきっかけは?
中学校では美術部にも入っていましたし、物づくりや絵を描くことは好きでした。でもこの分野で食べていくのは競争率も高いし、難しいだろうと早々に諦めて(笑)、服だったら周りに作っている人もいないし、やっていけるかなと考えたんです。
じつは小学生の頃から集団行動が苦手で、班活動でも黙々と一人で作業してしまうタイプでした。当時は自分にはコミュニケーション能力がないと思っていたので、物づくりなら誰とも関わらず一人で生きていけるかも、という狙いもありましたね。いざこの仕事に就くと、人間関係と切っても切れないと分かったわけですが(笑)。
衣装制作への思いが強くなったきっかけは、ビジュアル系バンドにハマったことです。中学生の時、音楽番組に出演していたあるバンドのギター担当が、楽器を弾かずに踊っていたのを見て「こんな魅せ方があるのか」と衝撃を受けたんです。生歌で、演奏も彼らの音源を使っていましたが、その演出はショーとして、音楽のみならず目で観ても楽しめるよう考え抜かれたものでした。
知れば知るほど、観客をとことん楽しませる究極のエンタメ性に心惹かれ、私も衣装という分野を極めて舞台づくりに参加したいと思うようになったんです。中高時代は独学で、リボンやフリル、裾の広がったスカートなどが特徴のロリータファッションを制作して、休みの日に自分で着て楽しんでいました。頻繁には上京できないので、静岡市内にあるビジュアル系バンドが出演するライブハウスに通っていましたね。
大衆演劇一座での衣装方もしていたそうですね。
服飾の専門学校を出た後は、そのまま都内の古着屋で洋服のほつれや破れを直すリペアの仕事をしていました。27歳の時にSNSで劇団の衣装方募集を知り、入団したんです。大衆演劇の役者は白塗りで、使う楽曲もロック調とあって、意外にもビジュアル系に通じるところがあるんですよ。
団員が10名に満たない劇団だったので、衣装の他にも大道具から照明までなんでもこなしていました。でも、照明を担当する時の自分は、お客様から見れば「照明さん」。衣装の道を極めたいのに、というもどかしさもありましたね。そのぶん、早く誰からも衣装方だと認められたい一心で仕事に打ち込みました。毎日ミシンを触っていましたし、舞台の幕と一体化した衣装を作るなど新しい試みもできたりして、貴重な経験を積めた5年間でした。
一般的に、舞台芸術において衣装や照明、大道具などは「裏方」と表現されることがありますよね。舞台に立つ役者自身も「裏方さんあっての私たちだから」と感謝を伝えてくれることがあります。理解はできるけど、私の中ではなんとなく違和感があって……。舞台に立つことが叶わないから“仕方なく”衣装をやっているわけではなく、衣装に憧れて、衣装が作りたくてこの仕事をしているんだと広く知ってもらいたいですね。主役からの感謝を期待しているわけではなく、私はその先にあるお客様の満足や感動を大切にしたいんです。
衣装制作に限らず、舞台という総合芸術を完成させるには、関わる人全員が役割をまっとうすることが重要です。号令の下にみんなで一緒に作ろう、と進めていくよりも、個々がひたむきに全力を出して作るものが集まった結果、いい舞台になるという考え方のほうが、私にはしっくりきます。もちろん表に出る役者にも輝いてほしいし、お客様にも感動してもらいたい。その姿を見たいから、衣装担当として本気で向き合うのです。

衣装づくりを通して
人とつながる
富士市にアトリエを構えた経緯は?
地元にUターン後、しばらくは自宅で受注制作をしていました。そのうちに、少し活動範囲を広げたくなり、富士市が募集していた『まちなかLabo』という、空き店舗を利活用しつつ中心市街地を活性化させることを目的に、起業・出店を目指す人を市と支援機関が連携して支援する事業に挑戦しました。
商店街で作品を販売する2週間のテスト期間では、完全に衣装でいくのか、一般のお客様が手に取れる洋服にするのか決め切れず、すごく中途半端なものを陳列してしまったんです。当然、一般の方の反応は芳しくなくて、手持ち無沙汰な時間が過ぎていきました。そこで、ミシンを持ち込んでその場で作業をすることを思い立ちました。通りから見えることでほどよい緊張感もありますし、作業をしながら作品を見てもらって、街の人と会話ができました。そのやり方を進めるうち、「このスタイルでやっていこう」と心が決まりました。
2020年3月に『アトリエテチ』として正式にオープンして、翌年には『観るは法楽』と名付けたまちなかアートフェスを主催しました。店舗に作家の作品を展示するイベントですが、私自身が作家さんとお店の個性を知った上でていねいにマッチングしていきました。
作家さんそれぞれに価値観や個性があり、その作品は作家の魂。だとすれば、店主にとってお店は大切な作品であり、魂ですよね。商店街という範囲内で単純に割り当てることはしたくなかったんです。作家と店主それぞれと対話して、さらに三者で思いを共有する過程を大切にしました。やり取りの中で齟齬が生まれないよう、参加者全体でのLINEグループは作らず、つねに一対一でと心がけましたね。開催期間中はポスターが剝がれていたり汚れていたりすると、誰かしらが直してくれました。私が頼りなく見えたからかもしれませんが(笑)。一人でやっているように見えて、実際はみんなが協力してくれたので、知らない間にチームができていたような感覚です。
アトリエを構えて、自分の居場所ができた時から、とたんに生きやすくなったと感じています。安心できる居場所が大事だと知ってはいたけど、こんな風に実感できたのは初めてで、自分でも驚いています。
そんな“居場所”でこれからやりたいことは?
まずはこれまでと変わらず、衣装づくりに向き合っていきたいです。数年前には、中高時代に憧れていたビジュアル系バンドの衣装を作る機会に恵まれました。雑誌の表紙やCDジャケットにも使われ、関係者用のCDまでいただいて、一つ夢が叶ったんです。たびたびあることではないけど、これからも真摯に続けていけば、また憧れの人から声がかかるはずと、ワクワク信じて待っています。
また、来年3月には吉原商店街を舞台に、アートフェスにバンド演奏や芝居を加えて進化させた総合芸術祭『百花繚乱春至為誰開』を開催する予定です。衣装から生まれたつながりをもとに、他にはない面白いものを実現させたいです。
今でもコミュニケーション能力に自信があるとはいえませんが、アトリエという確固たる居場所があることと、衣装づくりが結んでくれる周りとの縁で、自然体でいられることに満足しています。ふだんから手を取り合っているわけじゃないけど、周りにはちゃんと見守ってくれる人たちがいる安心感があります。不思議ですけど、“一人”を確立したら、仲間が増えたんですよね。
Title & Creative Direction/Daisuke Hoshino
Text/Chie Kobayashi
Cover Photo/Kohei Handa
撮影協力:ほんいちパーキング

小川浩子
舞台衣装制作/アトリエテチオーナー
1984(昭和59)年6月25日生まれ(39歳)
富士市吉原出身・在住
(取材当時)
おがわ・ひろこ/吉原第一中、吉原商業高校(現・富士市立高校)卒業後、東京都内の専門学校で服飾を学ぶ。幼少期から物づくりを好み、中学からは独学で洋服を作り、衣装の分野に進む。ビジュアル系バンドのエンタメ性の高さに感銘を受け、中高時代には自作のロリータファッションに身を包み、その世界観を楽しむ。専門学校卒業後は、古着屋に勤めて接客やリペアに携わった後、大衆演劇一座に入団。衣装方として5年間経験を積んだ後にUターン。2019年に富士市の中心市街地活性化事業『まちなかLabo』に応募。2週間のテスト期間を経て、翌年3月には吉原商店街内に『アトリエテチ』をオープン。依頼主の要望に応え、着る人がその人らしさを十分に発揮できる衣装づくりがモットー。

Nutshell 〜取材を終えて 編集長の感想〜
初めて特別な衣装を着たときのことを覚えていますか?私がうっすらと記憶しているのは5歳の七五三のとき。紋付袴を着せられ、「こんなバカみたいな格好はイヤだ」と泣きわめいて困ったと母は言います。和装の窮屈さもさることながら、今思えばそれは、衣装によって自分の存在が「いつもの自分ではない何か」に強制的に変えられ押し込められてしまうことに対する恐怖だったのだと思います。
衣装というのははたして人を縛り付けるものなのか、それとも自由にするものなのか。言うまでもなく「衣装」は文化人類学上の一大テーマですが、人類史の大半においてそれは個性を開放するためのものではなく、むしろ個人の個性を隠して社会に同化させる機能のほうが主でした。軍人や学生の着る制服も、パーティーのための正装も、平安時代の十二単や冠位を示す束帯も、現代のビジネス・スーツも、所属する組織や階級と一体化しその役割を演じるために着るもので、いわば「他人に合わせる」ための衣装です。
自分の着るものを自分で自由に選んでいいよ、という世の中になってきたのはわりとつい最近。なりたい自分になる、純粋な自己表現のための「衣装」というのはかなり現代的なトレンドだと思います。ステージ衣装にしてもコスプレイベントでの仮装にしても、あるいはちょっとしたお出かけの服にしても、自分でしつらえた特別な服を着て、本当になりたかった自分を楽しむ。そんな夢を叶えてくれる小川さんって、なんだかシンデレラの魔法使いみたいですよね。
- Face to Face Talk
- コメント: 0
関連記事一覧

Vol. 161|吉原山妙祥寺 副住職 川村 孝裕

Vol. 134|山大園 店主 渡辺 栄一

Vol. 147|東京農業大学応用生物科学部 准教授 勝亦 ...

Vol. 196|シェ・ワタナベ オーナーパティシエ 渡邊隆...

Vol. 183 |絵と造形 山下 わかば

Vol. 157|ジオガイド 津田 和英

Vol. 146|造形作家 あしざわ まさひと

Vol.215 |陶芸家 芦澤和洋
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
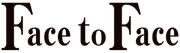










この記事へのコメントはありません。