古墳時代のスルガの王に思いを馳せて

愛鷹山を水源とし、「湧水で目を洗うと眼病が治る」との伝承も残る東光庵の湧水池
お出かけレポート
当時私は奈良にいた。今から20年近く前のことだ。仕事の関係で、平城宮跡歴史公園を月に1回くらいの頻度で幾度も訪れていた。それから数年後、私は再び奈良にいた。息子の下宿先である大和西大寺に、彼の在学中何度か通った。大和西大寺は奈良線・京都線・橿原線が交差する近鉄線のターミナル駅であり、前述した平城宮跡歴史公園の最寄り駅でもある。奈良そして平城宮は、言わずと知れた古墳や遺跡の宝庫である。果てしなく広い敷地に残る大きな柱の跡や、いまだに続く発掘作業を目にするたびに、なんとも言えない不思議な感情が湧き上がったのを今でもよく覚えている。
話は変わるが、『県民の日』なるものがあることをご存じだろうか?1871(明治4)年の廃藩置県から始まり、何度かの合併により1876年8月21日に静岡県が誕生。120周年にあたる1996年に『県民の日』とする条例が成立した。これを記念し、9月21日に『県民の日ウォーク愛鷹の古墳と湧水めぐり』が、ぬまづ観光ボランティアガイドによる企画で実施された(イベントの実施は8~9月の期間が認められている)。愛鷹山麓・金岡地区の古代から明治時代、今日までの歴史を探りながら歩くというものだ。
古墳と聞き、かつて奈良に通っていた頃を思い出した。奈良では、道を歩けば遺跡に当たる、というくらいたくさんの古墳があった。それらを避けるように道が造られ、目的地はすぐそこなのに大回りしないと辿り着けない、そんな場所ばかりだった。筆者が住むここ沼津の古墳はどんな感じなのか?この機会を逃す理由はなかった。
愛鷹山麓の古墳散策へ、いざ!
イベント当日はとても暑かった。暑さを避けるためイベントが認められている期間ギリギリまで後ろ倒ししたそうだが、近年の猛暑はその思いすら跳ね除けるらしい。目玉は市内にある二つの古墳、高尾山古墳と長塚古墳だ。古墳というと、木々が生い茂っていたり土が盛られていたりといった、形がはっきりと分かるものを(筆者は)想像するのだが、教科書でよく目にするようなそれとは違い、ちょっと拍子抜けしている自分がいた。
気を取り直して観光ボランティアの熱心な解説に耳を傾けてみる。高尾山古墳は全長62メートルもの大きさで、3世紀代に造られた東日本で最古級・最大級の前方後方墳。発掘された品々から、東日本の中でも大きな権力を持ち広く交流していた王の墓だとされている。長塚古墳は高尾山古墳より300年ほど後に造られた前方後円墳だ。埋葬施設は盗掘により破壊されているが、出土品から愛鷹山麓とその周辺を支配した首長が眠っていたとされる。このような説明を聞くだけで、スルガの地にもそのような古~い歴史があったのだと改めて感じさせられる。

全長62メートルの高尾山古墳を上空から見た全景(提供:沼津市教育委員会)

高尾山穂見神社はもともと古墳の上にあったため盗掘されなかったといわれている

全長62メートルの高尾山古墳を上空から見た全景(提供:沼津市教育委員会)
古墳から出土した埴輪などの埋蔵品が展示されている沼津文化財センターに、後日足を運んでみた。圧巻だったのは復元された高尾山古墳の主体部だ。眠っている王が今にも起き上がってきそうな、そんな感覚に襲われた。また、ショーケースに入れられることなく展示されている土器などを目にすると、当時の日常生活や宴のようすが音を立てて蘇ってくるようだった。

発見時の状態を再現した高尾山古墳の主体部(沼津文化財センター展示)

長塚古墳から出土された埴輪や土器の数々(沼津文化財センター展示)
市民でありながらまだ一度も足を踏み入れたことがない、沼津市明治史料館。ここは沼津の教育や住民の暮らしに尽力したことで知られる、沼津ではあまりにも有名な江原素六の屋敷跡に造られたものだ。ボランティアの解説を聞くまで知らなかったのだが、沼津は明治の世に静岡へ移住してきた徳川家により兵学校が作られたことを起源とし、非常に教育が進んだ町だったそうな。我が母校の設立者も江原素六であるということを、これまた初めて知った。じつに、筆者にとって「初めてづくし」のイベントとなった。現在は改修工事中で来年2月に終わる予定である。春になったらダッシュで、改めて見学に行こうと思う。
最後に、本イベントを企画した『ぬまづ観光ボランティアガイド』を紹介しよう。今年で21年目を迎えたぬまづ観光ボランティアガイドは、市民による無料奉仕の観光ガイドだ。年に数回の企画イベントの他に、週末には沼津港大型展望水門『びゅうお』や沼津御用邸記念公園で観光客向けにガイドを行なっている。60名以上いるスタッフのバックグラウンドはさまざまだが、共通するのは皆さん勉強熱心で、沼津をこよなく愛しているということ。県民の日ウォークでは、猛暑の中での力のこもった解説や、少々の坂道でもへこたれない鍛えられた足腰に頭の下がる思いだった。

ぬまづ観光ボランティアガイド理事の永岡さん(右)とボランティア1期生のスタッフ

丁寧に作られた資料とともに現地で解説していただいた
(ライター/reiko)
『愛鷹の古墳と湧水めぐり』 ウォーキング経路
金岡地区センター出発 ~ 東光庵の湧水池 ~ 高尾山古墳 ~ 金岡小学校跡碑 ~ 江原素六の墓 ~ 長塚古墳 ~ 沢田学校所跡碑 ~ 敬身舎・甲子塔碑 ~(武井牧場で休憩)~ 山田源次郎碑 ~ 沼津市明治史料館(外観)~ 金岡地区センター解散
ぬまづ観光ボランティアガイド
沼津市大手町1-1-1 アントレ2F
NPO法人沼津観光協会内
TEL:055-964-1300
高尾山古墳・長塚古墳
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/profile/bunkazai/kofun/index.htm
沼津文化財センター
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/shisetsu/bunkazai.htm
沼津市明治史料館
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/shisetsu/meiji/index.htm
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
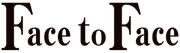
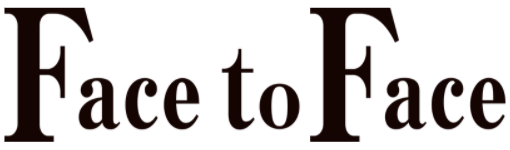
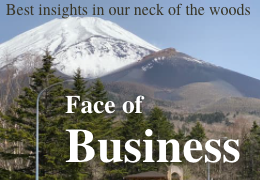
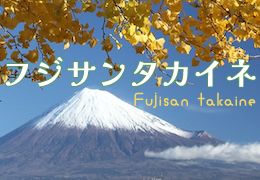

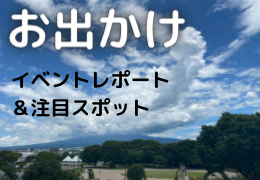











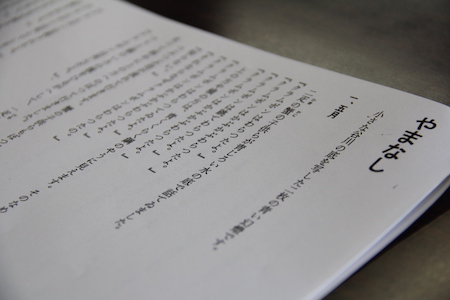

この記事へのコメントはありません。