空気感を纏う

さくらの音色 第5回
初夏に近づくと、冬眠から覚めたかのように急に「パーッとお出かけしたい!」と思い立つことはありませんか?「明日ディズニーシーに行こうよ!」と真夜中にLINEを送ると、「東京駅6:30集合ね!」とふたつ返事をしてきたノリの良い友達がいて驚きました。ノリが良すぎて、柔軟性が抜群すぎて、「これ、仕事に活かせたらいいのに、なんで遊びだと発揮できちゃうんだろうね〜」と笑いながら開園前の列に並び、夜は閉園まではしゃぎました。友達のノリの良さのおかげで、最高の休日を過ごすことができました。
歌舞伎の伴奏音楽として息づいてきた長唄にも『ノリ』という言葉があって、いわゆるテンポのことを指します。このノリを良い塩梅にするのが三味線弾きの技量なのですが、その匙加減に正解はありません。テンポがどのくらいという指示は譜面にも記載されておらず、結局のところ何がノリの良し悪しを決めるのかというと、「空気感」だと私は思っています。
空気感は、自然や物や場所などの環境だけではなく、他の奏者たちとの足並みや、さらには奏者本人の日常や人生が、どこかで影響してくるのかもしれません。だから人間国宝級の名人と同じ曲を同じノリで弾いたとしても「良いノリだったねー!」とは決して言われないでしょう。人生の歩みが違いますから。空気感はその場で造り出せるものじゃないよなと、つくづく思います。
「舞台って、非日常の空間なんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 でも私にとって舞台は日常の延長線上にあります。特別なものではなく、毎日練習してきた大好きな曲をそこで演奏するだけなので、やはり日常の延長線上なのです。だからこそ自分の味が滲み出る場でもあるのかなと思っています。
とはいうものの「本番なんてへっちゃらでーす!」というわけではなく、ドキドキしすぎて心臓が飛び出ちゃうんじゃないかと思うほど毎回緊張します。でも急に上手く弾こうと思ったところで、今さら無理ですよね。その場で何か新たな努力できるわけではないので。 結局のところ、舞台に出るまでの日常が表れるだけ、ということです。逆にその場で無理をして演奏する自分は自分ではないので、諦めも肝心。良い諦めもあるんですね(笑)。
緊張を消し去るもう一つの秘策が「耳を使う」です。目や頭が先に働きがちですが、耳を使って音の伸びを聴きます。そうすると必要ないものがすべてとっぱらわれる気がして、舞台を空間で捉えることができます。心がスーッとします。 そして自分はその空間に置かれている一つの個体であって、演奏自体は魂でしていることに気づかされます。幽体離脱的な感じ?あ、これは感覚の話なので変な人だと思わないでくださいね(笑)。
こういった体験をすると、心や魂こそはスーッとしていたいものだなぁと改めて思います。そんな時に浮かんでくるのが、小さな頃の思い出です。「あーたまーをーくーもーのー」とか「箱根の山は〜天下の険!」と、童謡や唱歌を歌いながらお散歩に行ったこと。近所を流れる田宿川の鴨に向かって「ガーガー」と真似てみたこと。夕飯を楽しみに待っている時の気持ちなんかを思い出すんですよね。幼い頃の些細な日常。今の私があるのは、そんななんでもない積み重ねがあったからなのだなと。

夏休みラジオ体操に行く私

今現在の私
私の演奏には今現在の練習の成果だけではなく、富士で生まれ育った歩みも見え隠れしているはずです。富士の空気感を纏った三味線奏者として、これからも演奏でハッピーを届けます!

佐藤 さくら子
長唄三味線演奏家
さとうさくらこ/富士市出身。3歳より長唄三味線を始める。富士高校、東京藝術大学音楽学部邦楽科、同大学大学院卒業後、2013年からプロの演奏家として活動。浄観賞、アカンサス賞など数々の受賞歴を持ち、現代邦楽アレンジや作曲も手がける。海外での演奏活動やテレビ出演も多数。東京と地元富士市の2拠点で長唄三味線の指導を行ない、伝統音楽を継承する一方、「親しみやすい三味線」を重視した演奏の自由化にも取り組んでいる。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
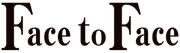
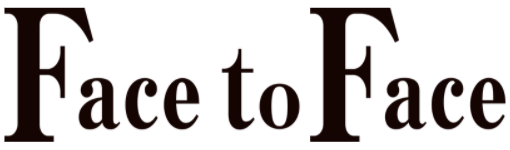
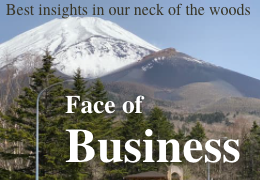
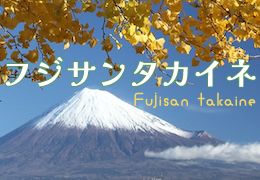

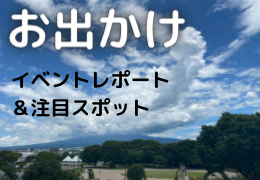









この記事へのコメントはありません。