人生100年の時代、「最期はどこで……」7

在宅介護編
この原稿を書いている最中、義母が永眠したという知らせが入居先の高齢者施設から届きました。6年前に同居を始めた頃、義母は自宅で過ごす日常生活をとても気に入っていて、将来的な介護の話題に触れると不機嫌になり、高齢者施設に入るなどあり得ないという雰囲気でした。
そんな義母が「施設に入ってゆっくり過ごしたい」と言いだしたのは、腰痛や股関節痛が悪化して自力で歩くことが困難になり、重ねて軽い心不全を患いカテーテル手術を受けるため入院したことがきっかけでした。それまでの間は、要支援2の介護認定を受け、自宅内の至るところに手すりを設置したり、私たちが仕事で不在の時にはホームヘルパーさんに昼食を作りに来ていただいたりと、さまざまな介護予防サービスを利用しながら自宅で過ごしてきたのですが、たびたびの体調不良で自宅での暮らしが不安になったのかもしれません。
施設には約4年間お世話になりましたが、面会に行くたびに、「ここにいればやりたくないことは何もしなくていいし、のんびり過ごせるわ」と話した義母の穏やかな笑顔が目に浮かびます。
最期まで自宅で暮らす
介護という現実が迫り、高齢者施設への入居を選択肢として考えた時、本人の心理的な抵抗、介護する側の罪悪感、費用面の負担など、さまざまな葛藤や課題が浮上します。施設に移り住む場合、「好きな時間に起き、食べたい時に食べたいご飯を食べるなどの自由度は維持できるのだろうか?」「貯金や年金で入居費用はまかなえるのか?」など不安は大きく、やはり介助を受けながらでも住み慣れた家で可能な限り暮らしたいと思うのが本音です。核家族化や高齢化が進む現代、介護サービスを利用しながら自宅で日常生活を送る一人暮らしの高齢者も少なくありません。
介護保険サービスとは
私たちは40歳になると介護保険の加入が義務づけられ、介護保険料の納付がスタートします。40~64歳までは第2号被保険者、65歳以上は第1号被保険者に区分され、第1号被保険者が要介護認定申請をし、介護が必要だと認定されると、原因を問わず介護保険サービスが利用できるようになります。
在宅介護サービスには要支援1~2の人が利用できる介護予防サービスと、要介護1~5の人が利用できる居宅介護サービスがあります。どのようなサービスをどれだけ利用するかなどはケアマネージャー(介護支援専門員)と相談しながら決め、作成したケアプランをもとに、自宅で生活しながら必要な介護サービスを受けられるようになります。
さまざまな介護サービス
◯ 訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー・介護福祉士)が自宅訪問し、食事・掃除・買い物などの「生活援助」、入浴・排泄などの「身体介護」を行う。
※医療行為はサービスに含まれない。要介護度によって利用できるサービスが異なる。
◯ 訪問看護
看護師が自宅訪問し健康状態の観察、服薬管理、褥瘡(ルビ:じょくそう)ケアなど医療ケア、健康管理を行う。
※主治医の訪問看護指示書が必要。
◯ 訪問リハビリ
病院や介護老人保健施設の理学療法士・作業療法士が自宅訪問し、心身機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するため、歩行訓練などのリハビリを行う。
※主治医が必要性を認めた場合、サービスを受けられる。
◯ デイサービス(通所介護)
日帰りで施設に通い、入浴・食事・日常生活の機能向上のための機能訓練などを行う。
※要介護1〜5が対象。医療行為はサービスに含まれない。
◯ ショートステイ(短期入所生活介護)
介護老人福祉施設などに短期間宿泊(最短1日〜最長30日)し、食事や入浴などの日常生活の支援、機能訓練などを受ける。
◯ 福祉用具レンタル
できる限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、介護ベッド、車いす、歩行器、手すりなどのレンタルを介護保険で支援する。生活動線の安全を確保、家族の介護の負担軽減を図る。
知っておきたい在宅介護に関するサービス
自宅で暮らしながら利用できる介護サービスは介護保険制度によって提供され、利用者の費用負担は原則1~3割(年金を含めた所得により異なる)です。ただし、介護保険サービスは1ヵ月に利用できる限度額が設けられ、要介護度に応じて上限額が異なり、超えた場合は自己負担となります。なお、医師・歯科医師・薬剤師などが自宅を訪問して行なう管理指導、福祉用具の購入や住宅改修などは別途、支給限度額が設定されています。
在宅介護のメリットは、なんといっても介護費用負担が少ないことです。公益財団法人生命保険文化センターの『2024年度 生命保険に関する全国実態調査』によると、介護を行なった場所別の月額介護費用は、在宅が平均5.3万円、施設が平均13.8万円とされています(食費・日用品・医療費などは別途、要介護度や自己負担割合により異なる)。また、介護期間は平均4年7ヵ月で、約4割の人が4年を超えて介護を行なったとしています。
高齢者の暮らしを支えるサービスは、介護保険サービス以外にも、高齢者みまもりサービス・訪問理美容サービス・寝具クリーニングサービスなど、市区町村などの各自治体が行なう生活サポート(一部有料)、またゴミ訪問収集・通院・外出介助などの民間サービス(有料)もあります。
自宅で最期まで暮らすことを可能にしてくれる在宅介護ですが、施設入居と比較して経済的負担が少ない一方で、夜間も目が離せず家族が睡眠不足になったり、家族が外出中にボヤ騒ぎがあったり、老々介護で体力がもたないなど、同居する家族の負担がデメリットになる場合もあります。前回までもお伝えしたように、介護の不安・悩み・課題に直面したらまずは地域包括支援センターなどに相談し、専門家のアドバイスを受けながら介護の方向性を決めることが、本人・家族のどちら側から見ても大切です。
(ライター/山崎典子)
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
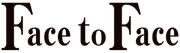
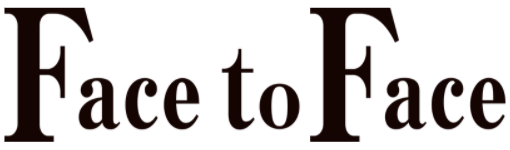
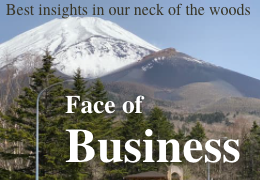
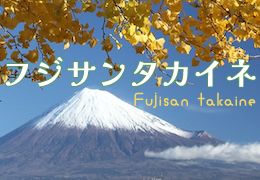

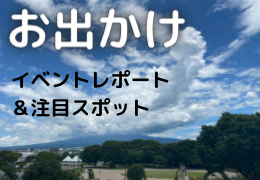













この記事へのコメントはありません。